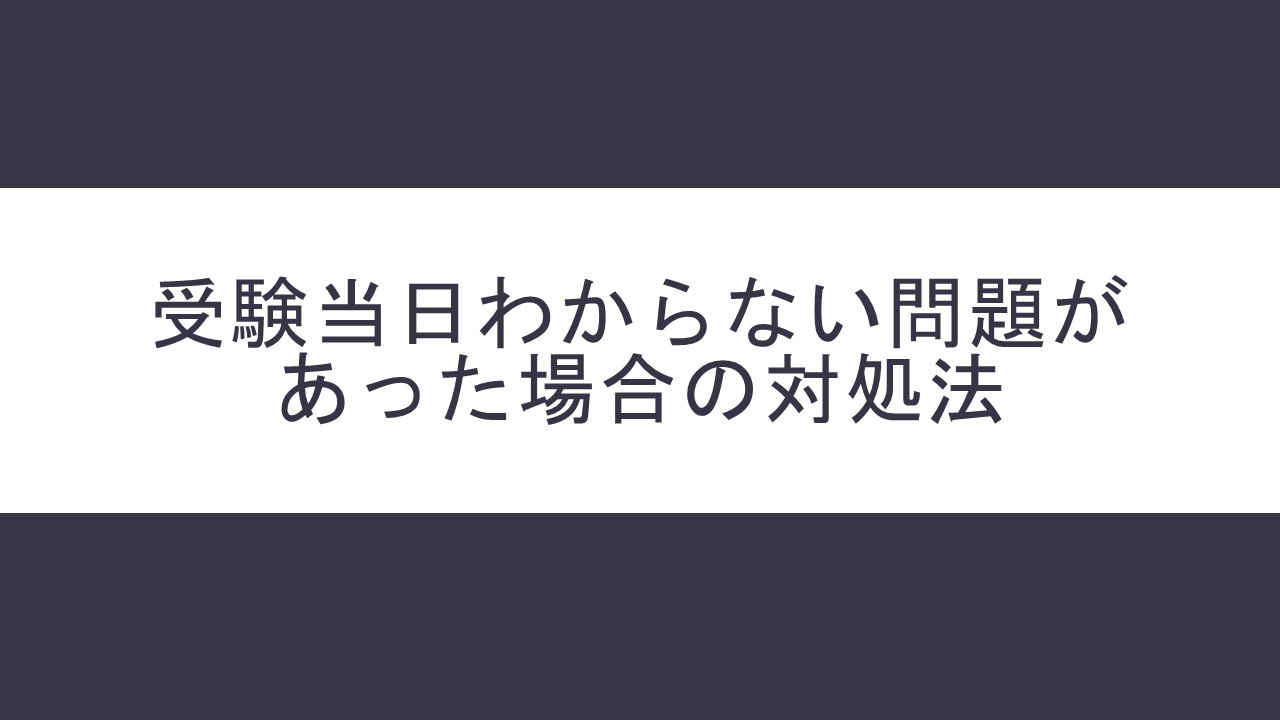受験の時にわからない問題があった場合、焦って余計に混乱してしまったりしたことはありませんか?
この記事では、実際受験当日にわからない問題があった時、どのように対処したらよいか?を、
クイズノックの伊沢さんとふくらPのTOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK! 天才LOCKS!」ラジオでのアドバイスや、対処法をまとめました。
目次
受験当日わからない問題があった場合
受験当日、わからない問題があった場合どうしたらよいですか?
中学3年生のリスナーさんからの質問に対して、クイズノックの伊沢さんとふくらPが答えていた内容をまとめました。
受験当日わからない問題があった場合~伊沢さんの対処法
伊沢さんの対処法
一旦解いて「これ、やめよう」という問題もありましたね。
そういうときは、必ずメモを残すようにしていました。
“どこまでやりました”、“ここまでやったけど、わからなかった”みたいなことを書いて、次にいくようにしていたね。
続いて、ふくらPの対処方法です。
受験当日わからない問題があった場合~ふくらPの対処法
ふくらPの対処法
飛ばす問題には2種類があります。
例えば一つ目は、かなり考えないと解けない問題です。
今の自分の知識量ではいくら考えても勘になっちゃう、思い出すとかではないタイプの問題の場合は、遠くに置いておかないといけない。
逆に“これ絶対に知っているはずなんだけど、ちょっと思い出せない”とか、“これ何かあったから、後で考えたい”みたいなのは、
近くに置いておきたい問題です。
そのため、まず、一周解き終わった後にすべき順番は、
1.近くに置いておいた問題を見直す
2.その後に既に終わった問題を見直す
3.最後に遠くにおいておいた問題をやる
という順番にします。
例外はありますが、やっぱり自分が1回埋めたものは、見直せば点が上がる確率が高いからです。
うっかりミスをしている場合は、そのミスに気づいたら、点数が上がる可能性が高いです。
すごく難しい問題よりは、先にやったほうがいいです。
僕も遠くに置く問題はただの白紙で、近くに置いておくものには印をつけていたかな。
東大卒の伊沢さん、東工大卒のふくらpは、受験の都度、このように対処をしていたのでしょう。
確かに、一度目に解いたものは
間違っていない・ミスをしていない
と、思い込みがちですが、当日の緊張などで、うっかりミスをしていることは多々あります。
落ち着いて再度解くことで極力ミスを減らすことが可能なのです。
また、
- 全くわからないものはまずは白紙
- 少し考えればわかりそうなものはマークをつける
というやりかたは、是非参考にされるとよいでしょう。
実際、テストを解いていると、焦ってしまって、どこでどのように悩んでとばしてしまったか、を、再度考える時間がもったいないのです。
何度も同じことを繰り返さないための時短テクニックとなるでしょう。
受験当日わからない問題があった場合に、最終的に白紙で出す?
わからない問題があった場合には最終的に白紙で出すのはどうでしょうか?
これに関しては賛否両論ありますが、
- 記述問題であれば自信がなくても書いたほうが良いでしょう
というアドバイスが多くみられます。
その理由としては、全く何も書かなかった場合は採点もされませんが、自分の考えを少しでも書くことで、先生方は受験生の様々な考え方を評価してくれる可能性があるからです。
是非、参考にしてください。
まとめ
受験の時にわからない問題があった場合の対処法は参考になりましたでしょうか?
入試はいつもとは違う空間で、必ず緊張をすることが予想されます。その時のために、まずはこういった環境を作ってなれること、そして、その時の対処法を一度でも練習してみることは子供にとって大切でしょう。
あわせて是非確認してみてください。
-

-
中学受験・当日のハプニングとは?出来る限りのリスクヘッジを
中学受験当日。自分の身に起こるかもしれないハプニング。 起こらなければよいのですが、もしものために出来る限りのリスクヘッジをこころがけたいものです。 この記事では、中学受験当日の起こる可能性があるハプ ...
続きを見る