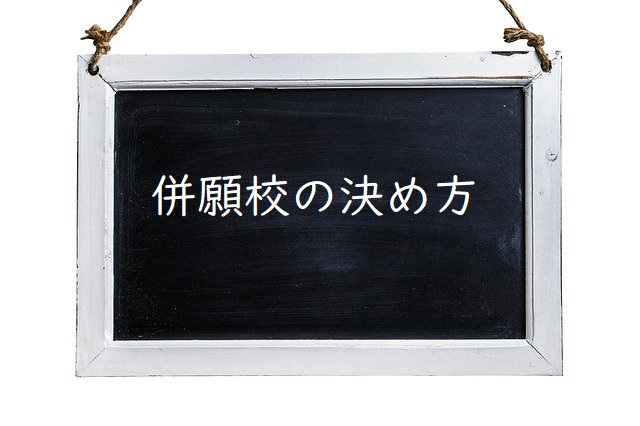中学受験は学力だけの戦いではなく、メンタル面も大きく結果を左右します。
そういった意味でも※併願校が果たす役割はとても大きなものになるでしょう。※併願校とは、第一志望の学校に合格できなかった場合の進学先確保のために受験する学校のことを「併願校(へいがんこう)」と呼びます。
併願校を決める際の基本的な考え方について、塾のアドバイスから、基本のパターンと、保護者のやるべき準備などをまとめました。
中学受検併願校の決め方は?
四谷大塚の先生のお話では、
- 本番前に合格校を確保できるように受験生の学力に応じてバランスよく併願パターンを組むことが基本である
ということでした。バランスよく、というのは次の3点があげられます。
- ①受験生の偏差値で合格可能性80%以上に達している、合格有望校
- ②受験生の偏差値が合格可能性80%に達しているか、その前後のもの、実力適正校
- ③受験生の偏差値が合格可能性50%に達しているかその前後のチャレンジ校
この①~③をバランスよく併願パターンに組み込むということです。
本番前には①の合格有望校を受験して、1校でも合格すると、本番前のプレッシャーが全く違ってきます。
この、お試し受験は、たとえ進学しない学校であっても小学生の心のプレッシャーが軽くなることがわかっています。大切なことは、
確実に受かる学校を受けるということです。
事前に合格校を確保しておけば、残りはチャレンジ校と、実力適正校でも安心して受験は可能です。
併願校選びは保護者が主導で
併願基本の決め方は上記でご理解いただけたかと思いますが、併願校選びにはとても時間がかかりますので、
保護者主導で動いてみてください。
特に、6年生になるとお休みの日は基本テストや特訓などがありますので、なかなか子供自身が動くことは難しくなってきます。
そこで、保護者のかたが沢山の学校を調べてみてください。
併願パターンは9月までには決めておくと、その時期から始まる過去問練習にスムーズに進むことが出来ます。
四谷大塚調べでは、第3~第4志望の学校でも通っているお子さんがほぼ100%に近いという結果が出ています。
ということは、併願校は心の底から納得できる学校を選ぶことが望ましいのです。
例えば、御三家の学校をチャレンジ校にする場合、定員と応募者数を考えると、半分以上の人が不合格になります。
そういった意味でも、チャレンジ校以外もしっかりと通うつもりで学校を調べたいものです。
その後のお子様の学校生活を楽しくさせることが出来るのは親の力が大きいでしょう。
併願校は偏差値だけでは選ばない
併願校においては、偏差値だけでは選ばないようにすることが大切です。
例えば、同じくらいの偏差値であれば、一番高い偏差値を選ぶのではなく、
- 校風
- 教育方針
- 学校のカリキュラム
- 大学受験の指導方法
- 学校説明会での学校の実際の雰囲気
- 通学距離や周辺環境
などを見て決めることが大切です。
実際、学校に通っている生徒達を見たり学校を見ると、自分の子供にあっているかどうかもわかります。
また、Web説明会やHPも要チェックです。
特に、コロナ禍の現在では、自立を重視するか、一人一人しっかり勉強を見てくれるか?なども大切になってきます。
ICTの環境なども重要です。
これらを総合的に考えて子供にあった学校を選びましょう。
まとめ
併願校は、9月までにはざっくりと決めておきたいとはいえ、ギリギリまで考えることも可能です。
沢山情報を収集して、是非、お子様にあった併願校選びが出来ることを願っています。
併願校選びで失敗したくない!といかたはコチラの記事もあわせて参照にしてみてください。何かヒントになるかもしれません。
-
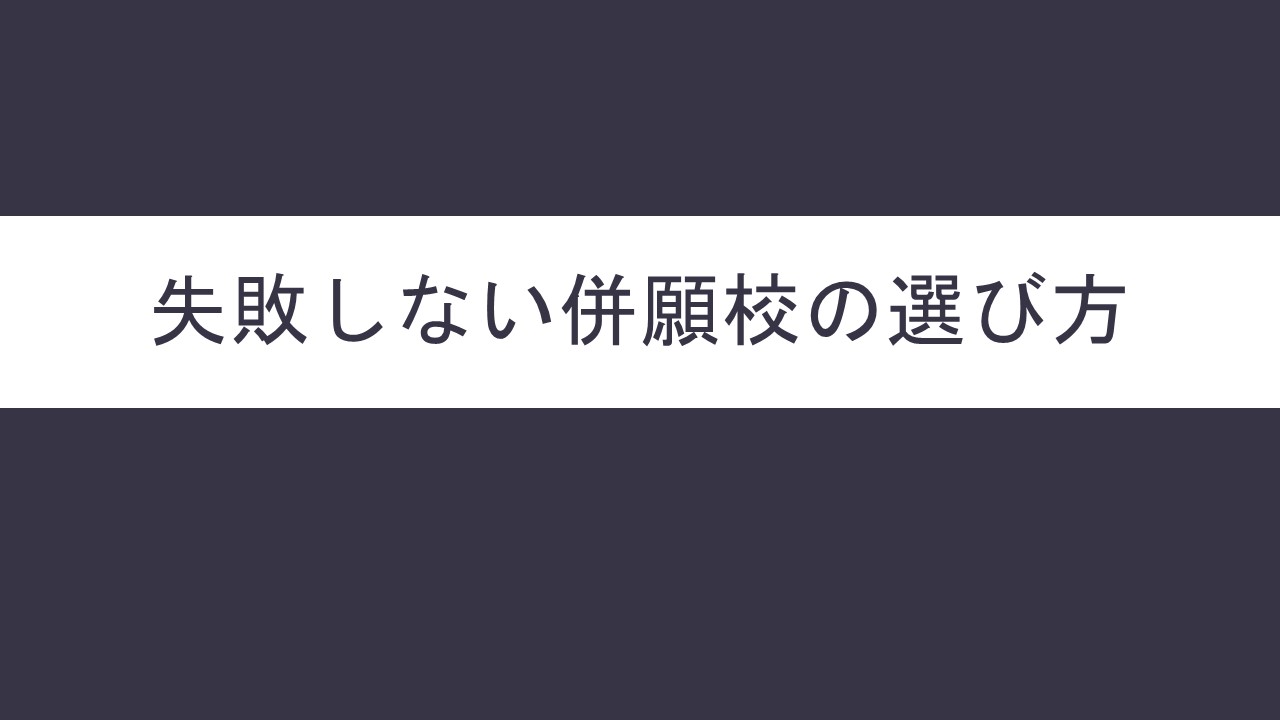
-
中学受験で失敗しない併願校の選び方とは?
中学受験の中で第一志望と同じように大切な併願校の選び方。 9月~12月初旬までには最終的な併願校を決めるというのが中学受験の通例ではあります。 とはいえ、ギリギリまで悩む併願校選び。 以前こちらのブロ ...
続きを見る